「最近、愛犬が何となく元気がない…」「食欲が落ちてきた…」そんなとき、もしかすると”肝臓”が関係しているかもしれません。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど症状が出にくく、異常が見つかったときにはすでに進行していることも少なくありません。
今回の記事では、犬の肝臓の役割や不調のサイン、日常でできるケア方法、そして肝臓サポートにおすすめのサプリメントをご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
犬の肝臓の主な役割

犬の肝臓は、体全体の健康を支える多機能な臓器です。
栄養の代謝とエネルギー生成
肝臓は、食事から吸収した栄養を体が使える形に変える「代謝工場」です。たんぱく質・脂肪・糖質を分解・合成し、必要に応じてエネルギーとして供給します。
有害物質の解毒
薬や食品添加物、体内で生じた老廃物などの有害物質を分解・解毒化します。この働きによって、血液や臓器がダメージを受けるのを防ぎます。
胆汁の生成と分泌
肝臓は胆汁を作り、胆のうを経由して腸に送り出します。胆汁は脂肪の消化吸収を助け、ビタミンA・D・E・Kなどの脂溶性ビタミンの吸収にも欠かせません。
免疫機能のサポート
肝臓には、細菌やウイルスを捕らえる免疫細胞が多く存在します。これにより、体内に侵入した病原体への抵抗力を高めます。
犬の肝臓トラブルの主な原因

犬の肝臓機能が落ちる背景には、さまざまな要因があります。
加齢による機能低下
犬も年を重ねると、肝臓の解毒や代謝の働きが少しずつ落ちていきます。特にシニア期に入ると、日常の食事や薬の影響を受けやすくなるでしょう。
食事や生活習慣の影響
高脂肪の食事やおやつの与えすぎ、添加物の多いフードは肝臓に負担をかけます。また、肥満は脂肪肝のリスクを高め、肝臓病の原因となることもあります。
感染症やウイルス
レプトスピラ症などの感染症やウイルスが、肝臓にダメージを与えることがあります。ワクチンや予防接種を怠ると、重い肝炎につながることも。
薬の副作用
長期間の投薬(抗生物質、抗てんかん薬、鎮痛剤など)は、肝臓に負担をかけます。薬を使う際は、獣医師の指導のもとで定期的に血液検査を行うことが大切です。
他の病気からの影響
心臓病や糖尿病、甲状腺の異常などが、肝臓に二次的な負担を与える場合があります。体全体の病気とつながっているのが、肝臓トラブルの難しいところです。
肝臓病のサイン

肝臓の不調は、初期には分かりにくいですが、進行すると次のような症状が出ます。
元気や食欲の低下
普段より散歩を嫌がる、寝ている時間が増える、ご飯を残す…など漠然とした不調が最初のサインになることがあります。
嘔吐や下痢
肝臓の働きが落ちると消化機能にも影響が出やすく、嘔吐や下痢を繰り返すことがあります。慢性的に続く場合は注意が必要です。
黄疸
肝臓で処理できない「ビリルビン」という色素が体に溜まると、目の白い部分や歯ぐき、皮膚が黄色っぽく見えることがあります。
お腹の張り(腹水)
肝臓の機能が落ちると、血流や水分の調整ができなくなり、お腹に水が溜まることがあります。お腹が膨らんできたら要注意です。
体重減少や筋肉の衰え
肝臓の代謝機能が低下すると、十分に栄養を吸収・利用できなくなり、痩せてきたり筋肉が落ちてきたりすることがあります。
肝臓ケアの基本

肝臓を守るためには、日常生活での管理が大切です。
食事管理を見直す
肝臓にやさしい食事は、最も大切なケアのひとつです。低脂肪・高品質なたんぱく質を中心にした食事や、獣医師が推奨する肝臓サポートの療法食を選ぶことで、肝臓への負担を軽くできます。
定期検診を受ける
肝臓病は初期症状が出にくいため、血液検査やエコー検査で早めに異常を発見することが重要です。年に1~2回は健康診断を受け、シニア犬であればさらに短い間隔でチェックすると安心でしょう。
生活環境を整える
添加物の多いおやつや人間の食べ物は、肝臓に負担をかけます。また、肥満は脂肪肝などのリスクも高めるため、体重管理も肝臓ケアの一環です。毎日の運動や適正体重の維持を心がけましょう。
肝臓サポートにおすすめのサプリメント
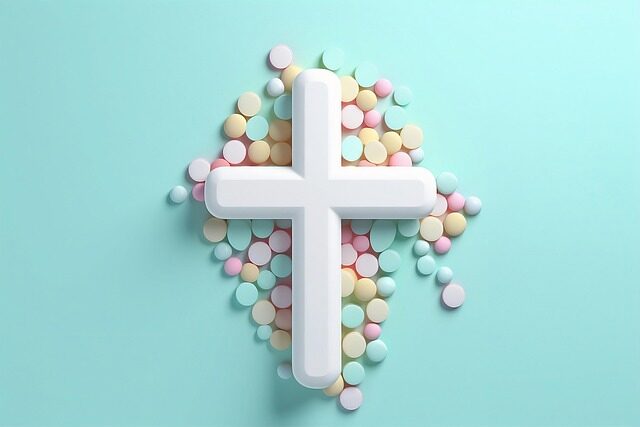
最後に、肝臓サポートにおすすめのサプリメントをご紹介します。
ヘパアクト
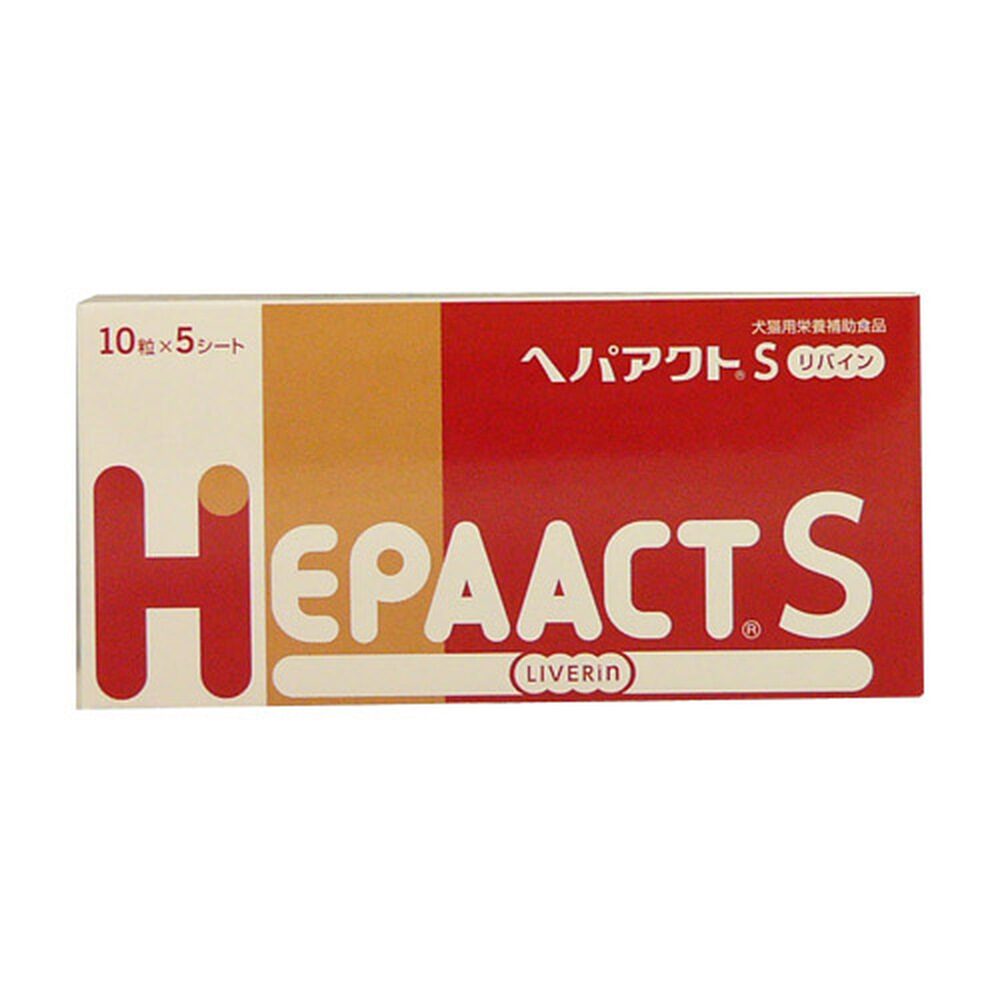
ヘパアクトは、犬や猫の肝臓を守るためのサプリメントです。肝細胞を守りながら働きをサポートしてくれるので、シニア期や肝数値が気になる子におすすめです。
URL:ヘパアクト
アンチノールプラス

アンチノールプラスは、関節や心臓、皮膚、認知機能など幅広い健康をサポートします。アンチノールプラスに含まれるモエギイガイ抽出物は、強い抗酸化作用を持ち、肝細胞を酸化ストレスから守ってくれたり、肝臓のダメージの進行を抑えてくれたりします。
URL:アンチノールプラス
プロへパフォス
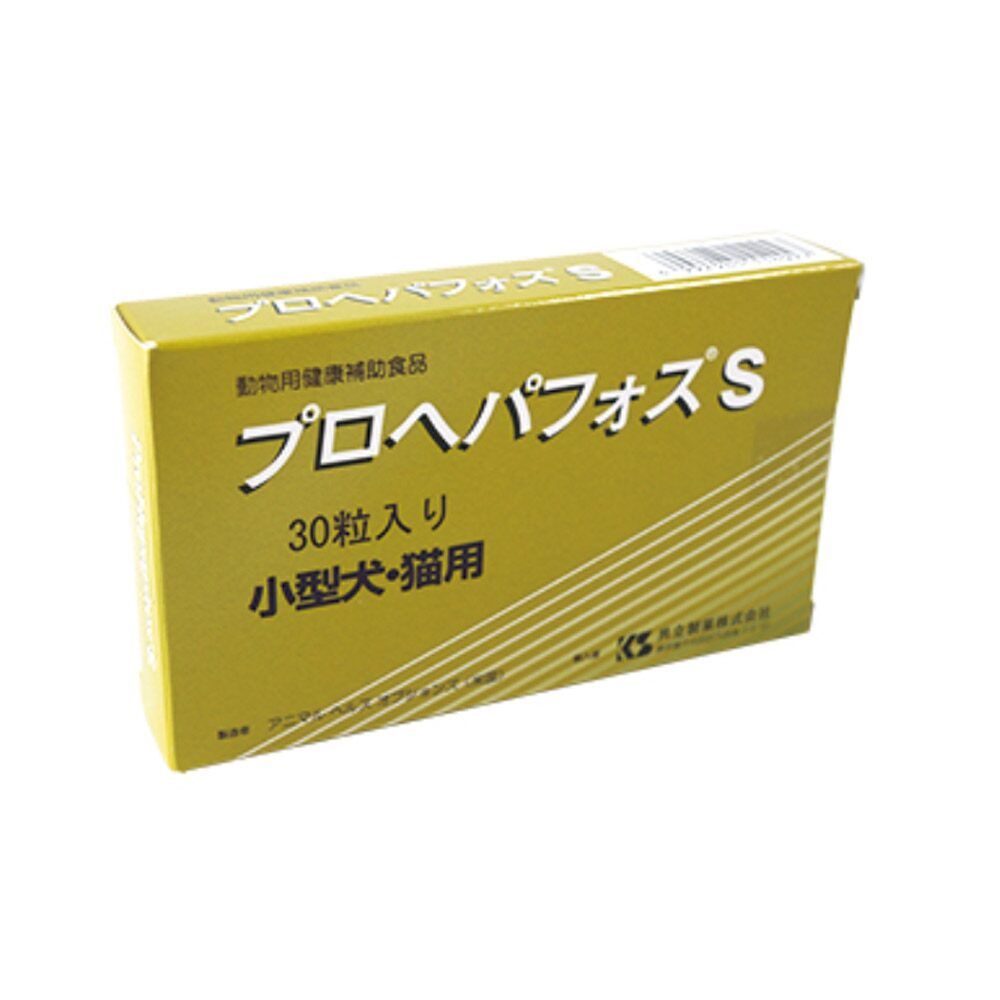
プロへパフォスは、肝酵素(ALT・ASTなど)の数値が高いときや、肝臓のダメージが心配される犬に動物病院で処方されることが多いサプリメントです。肝機能を維持し、体内の解毒作用や代謝をサポートする目的で用いられます。
URL:プロへパフォス
まとめ
肝臓は症状が出にくい臓器だからこそ、日々の予防と早期ケアが命です。食事・生活習慣・サプリメントを組み合わせることで、愛犬の健康寿命を延ばすことができるでしょう。
「うちの子も年齢的に心配…」という方は、まずは獣医師に相談しながら、健康診断を受けたり、サプリメントでのケアを検討してみてください。



コメント